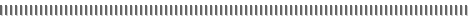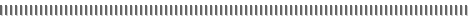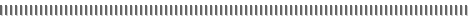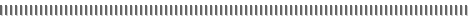|

ブタンガスボンベに付けているバルブは自分で作ったのかというお問い合わせをいただきましたが、残念ながら既製品で、リンク集に載せましたイギリスの Chedder Models の Gas Valve for Disposable Tank という製品です。
なお、その後 Chedder Models は Stuart Models社に吸収され、このバルブは同社から Gas Can Regulator という名前で販売されています。
ブタンガスボンベの口金のネジは、ミシン用の特殊ネジの1種で、直径7/16インチ、ピッチ インチ28山、ネジ山角60度のものだそうです。
工具店でそのサイズのタップを聞いてみましたら、細目のユニファイネジでもインチ20山で、そんな細かいピッチのものは特注品ではないかとのことでした。
となると自分で旋盤を使って切るほかなさそうですが、7/16インチの内ネジを切るのは大変そうですね。
追記
その後、YAMAWA製の7/16-28Uを入手しましたよというメールをいただき、その旨指示して工具店に注文し取り寄せてもらいました。
追記の追記
この7/16-28Uのタップで切った雌ネジをブタンガスボンベの口金にねじ込んでみたところ、きちんと根元までねじ込めません。
エッ?どうして??と、いろいろなボンベに試してみると 、軽くねじ込めるものがあったりして様々です。
原因はボンベのほうにあり、転造で刻んだであろうネジ山の形が大雑把で、タップで切ったユニファイネジ山とうまく合わないのです。
ちゃんとねじ込めるのは、液化ガスがボンベ内のスポンジにしみこませてあるタイプ、つまり液化ガスを模型用ガスタンクに移せないボンベで、それができる液化ガスがそのまま充填されているボンベには、きちんとねじ込めないものが多いのは困ったものです。
|